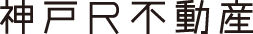第30話 Tumbling Dice
2012年 8月追記
干ばつから果樹を守るため、早朝から夜まで、雨乞い(水かけ)を続けています。

8月下旬、真っ暗になるまで水かけ。SSはちゃんとライトもウインカーも付いてて公道も走れます。
前話にも書いてますが、井戸も川もないラ・フランス園(約40アール)には、別の園地の井戸からSSのタンクに水を汲んで運んでって水かけをしなきゃなりません。(第29話参照)
ウチのラ・フランス園には井戸も川もない・・・って、実は、井戸はあるんです。
っていうか、正確には、井戸はあるけど水が枯れてしまったのです。

ラ・フランス園の古い井戸。サダコが出てきそうな佇まい。
30数年前に、父が近所の土建屋さんに頼んで掘った井戸。当初は水量豊富で、畑を潤してくれていました。ところが数年前から、夏場の一番水が必要な時期に、水が出なくなってしまったのです。地震か何かの地殻変動により、水脈がずれてしまったと思われます。
昨年の震災でも、有名な温泉が出なくなったという被害もあったみたいですから、地下水の水脈が変わってしまうのは、珍しくないことみたいですね。。
でも、今年はほんとに暑くて降水量が少なく、深刻な干ばつです。
この井戸さえ水が出てくれたら、わざわざSSで運んで水かけなんてしなくていいのに・・・
・・・この井戸さえ・・・
という切実な悩みを解消するため、近くの井戸堀やさん(仮称)に相談してみると、水脈の調査をしてくれることになりました。古い井戸の下に水脈があれば、井戸の底にパイプを打ち込んで深層の地下水を汲み上げることができます。
水脈調査の当日、うまく水脈見つかるかな?どんな方法で水脈調査するんだろう?きっと超音波かなんかを使った最先端の機械でも持ってくるんだろうな。。
ってワクワクしながら現場に行ってみると、井戸掘やのおっさんが、何やらどっかで見たような金属の棒を両手に持って井戸の周囲をウロウロしているじゃありませんか。
・・・?
・・・あれは・・・たしか・・・ダウジング?!
・・・マジか?

こんな感じで水脈調査してました。鉄の棒を使った ロットダウジングというそうです。
ずっと前、「○○の埋蔵金を探せ!」的なテレビ番組で見たことある光景。
それが実際に目の前で行われているなんて・・・
素人ならともかく、プロの井戸掘やさんがダウジングで調査するのか?何か科学的な機械じゃないのか?と、最初は戸惑いを隠せませんでした。
が、井戸掘やさんは「大丈夫だ」と自信満々で歩き回ってます。
画像のように鉄の棒(ロット)を両手に持ち歩き回って、地下でなにか反応するとロットが開いたり左右に動いたりするのだそうです。
※農業?豆知識 ダウジング・・・ダウジング(Dowsing)は、地下水や貴金属の鉱脈など隠れた物を、棒や振り子などの装置の動きによって見つける手法。ダウジングをする人はダウザーと呼ばれ、歩きながら分岐した枝や曲がった金属片、軟らかい針金、小さい振り子などを使用する。ダウジングが地下の水道配管や水脈、鉱脈に反応する確率は、それらの仕事に従事もしくは専門の知識と経験則を持つ者が使用すると高確率となり、ダウジングを用いない場合であっても割り出しの発見率は同等であるとされている。近年、日本において科学者及び技術者らがグループとなり、L字型棒による探索法についての検証、追試実験を行った結果、地中にある埋設物の検出能力は全く示されない事を学会において発表。
・・・ん?・・・科学的には、ダウジングには埋設物の検出能力は全くないって・・・
でも、調べてみるとダウジングは今でもプロに結構使われている調査手法らしいんです。
科学的には効果なしだとしても、プロがあれだけ自信たっぷりにやってたんだから・・・
まあ、科学では解明できないこともたくさんあるし・・・任せておくか。。
ということで、不安と驚きに満ちた調査の結果、やはり古い井戸の下には水脈はなく、井戸から約2メートルずれた位置に水脈がみつかりました。ところが、横の位置はわかっても深さ何メートル掘れば水がでるかは、やってみなければわからないというんです。
・・・それでいいのか?
・・・井戸堀って、そんなものなのか?
と、さらに不安は増していましたが「1日か2日で簡単にできる。おたくの予算でなんとかすっから」という、かなりアバウトな見積りにより、新たに井戸を掘ってもらうことにしました。
古い井戸は「堀井戸」というタイプで、重機で掘って地下水面に達したところで孔壁としてコンクリートの土管を埋め込んだもので、深さ約8メートル、土管の直径が約1メートルの井戸でした。この方法は重機を使うためお金がかかります。
新しい井戸は「掘抜き井戸」というタイプで、地上から棒状のもので穴を掘って細い水管を差し込み地下水を汲み上げる井戸。一般的にはボーリング工法で掘るのですが、ボーリングの機械が必要となりお金がかかってしまうので、今回はボーリーングせずに直接鉄管を地下水面まで打ち込んで水を汲み上げる簡易的な方法で掘ってもらうことに。
ところが、古い井戸を重機で掘った際の埋め戻しのときに埋設されたと思われる大きな石やコンクリート片などが2~3メートルの深さのところに埋まっていて、数メートル打ち込むと埋設物にぶつかりなかなか鉄管を差し込めず、結局、上層部分を重機で掘り邪魔になる埋設物を撤去してから鉄管を打ち込むという、二度手間な工事になってしまいました。

井戸掘りの現場。右手前が古井戸。

まず、小型ユンボで深さ約3メートルくらい掘って・・

鉄管を打ち込んで約10メートルの深さまで到達。(残念ながら打ち込み作業の画像はありません。)

ガチャポンを取り付けて・・・ついに水が出ました!

一応、これで完成。
ガチャポン(手押し式ポンプ)で水を出して水量を測りながら使用し、水量が安定しないようなら鉄管を継ぎ足してまた打ち込むらしいです。
それにしてもガチャポン、優れものです。電気も燃料も使わず、人力で地下水を汲み上げることができるのです。地下水さえ豊富なら、いくらでも不足のない量の水を汲み上げられます。ハンドルに連結されたピストンの圧力で水を吸上げる、という単純な理屈ですが、これを考えた人って偉い!
それに、ガチャポンっていうネーミング。ガチャガチャと動かして水を汲み上げるポンプだからガチャポン?・・・とにかく、わかり易いネーミング。このネーミング考えた人も偉い!
ということで、なにしろ待望のNEW井戸が完成。

ポンプをつないで稼働中。
ガチャポンの下部に配管を分岐させバルブを設置して、ポンプとスプリンクラーをつなげば、効率よくラ・フランスの木に水をかけることができるようになりました。
・・・でも、当初の予定になかった重機を使ったり、予定ではかかっても2日と言っていた工事期間が結局4日かかったり・・・金、いくらかかったんだろう?(まだ請求きてません)
・・・しかも、井戸掘りが終わった途端、井戸掘やさんたちがまだ現場にいるうちに、イヤガラセのように雨が。・・・通り雨だったらしく、雨はすぐに止んで、空には井戸の完成を祝うかのように(自然への無駄な抵抗をあざ笑うかのように?)虹がかかっていました。

突然の雨、その後には虹が。
・・・井戸掘り、究極の「雨乞い」か?
そして、古い井戸は当分そのままにしておくつもりでしたが、せっかく重機持ってきたんだから・・・という井戸掘やさんの好意(?)もあって、埋め戻すことになりました。

埋め戻す前の古井戸。いままでありがとう。
すると、井戸掘やさんの親方が、「井戸さは水の神様いっから、ただでは埋めらんねぇんだ。お祓いすっから"梅"と"葦(ヨシ)"ば用意してけろ。」というのです。
・・・なるほど、昔かたぎの職人は、そういう伝統やしきたりを大事にするんだな。。
と、大急ぎで"梅干"と"ヨシ"を用意して持っていくと、それをおもむろに井戸に投げ込み、お酒と塩で清めて埋め戻しをはじめました。重機があれば、土管を取り外して埋める程度のことはあっという間に完了。
とにかく、新しい井戸掘りも古井戸の埋め戻しも順調(?)に終わった。。
と、ホッとしたところで、最後に親方がボソっと一言。
「"梅"と"葦"っていうのはよ、ウメてヨシってことでよ。祟りがないようによ~。」
・・・ダジャレかい!
つづく
 このブログについて
このブログについて山形R不動産メンバーの水戸靖宏が、ある日突然兼業農家になり、戸惑い、苦悩し、時折愚痴を言いながらも、楽しく農地と向き合っていくストーリー。後継者不足で増え続ける空き農地。山形R不動産では物件ばかりではなく、農地や農業も紹介してしまうのか!?
 著者紹介
著者紹介水戸靖宏(山形R不動産/千歳不動産・マルアール代表)
山形R不動産の代表であり、千歳不動産株式会社の代表取締役、そして株式会社マルアールの代表も務め、さらに現役の兼業農家として、ラ・フランスやさくらんぼを栽培。


















![[団地を楽しむ教科書] 暮らしと。](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/rincglobal/common/thmb_kurashito_book.png)